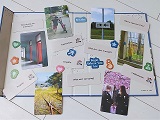オープンバッジで組織開発への思いを確認する
少し前に「オープンバッジ」が届きました。
10年以上前、2013年に取得した
システムコーチング
(ORSC:Organization & Relationship
Systems Coaching)
CRRグローバル認定プロフェッショナル
システムコーチのデジタル資格証明書だそうです。

デジタル資格証明書をどんなふうに使うのかは
まだピンときていませんが、
組織開発のツールの
「ソウル・クリーチャーズ・ランド」と
Points of You®の「Speak Up」を
最近立て続けに手に入れたこともあり、
久しぶりにORSCの学びを思い出して、
今年の後半以降は、
チームビルディング、リーダーシップなど
組織開発、組織づくりに力を入れていくことに
なるのかなという予感が芽生えています。
もともと組織に対する思いはとても熱いので、
暑い?熱い?うちに、形にしていきたいです。