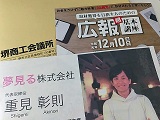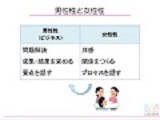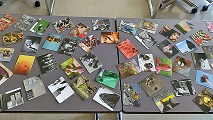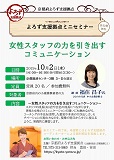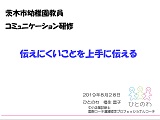堺商工会議所で女性限定セミナー
「共感力を活かすコミュニケーション力UP」を
開催しました。
働き方改革、生産性向上が叫ばれる今、
女性(女性性)が持つ共感力が「ひとのわ」をつなぎ、
働きやすい職場をつくるために求められていることを
力説し、あとは、演習三昧で聴く力を磨きます。

Points of Youの写真カードを選んで、
どう感じたか、どう見えたかを自由に語ります。
思いもよらない見方や発想で語る相手に好奇心を向け、
おもしろがって聴いてみると、
初対面の人とこんなに話せるの?という声が出るくらい、
心を開いて本音や夢が語られます。
中には、友人にも話していないお悩みを打ち明けたり、
私、こんなこと考えてたんだ、と驚いていたり、
笑顔があふれ、そのエネルギーに圧倒されます。

職場でもこんなふうに聴けるの?話せるの?と
思われるかもしれませんが、
1回あたり、1人が話した時間は3~5分です。
お仕事中におしゃべりに興じるのではなく、
短い休憩時間やちょっとした空き時間、
立ち話でも歩きながらでも話せる時間です。
「そうじゃなくて、」と遮る代わりに、
「へ~、それで?」とおもしろがって
ほんの数分耳を傾けるだけで、
人と人がつながり、職場の雰囲気がよくなります。
だからといって、
毎回毎回、聴かなくてもいいんです。
余裕がないときに、無理に聴かなくていいんです。
あー、聴いてあげればよかったなぁと思った後や、
気持ちに余裕ができたとき、
何かあったのかな?と気になったとき、
今日のセミナーで好奇心全開で聴き合った体験を
思い出して、
職場の居心地がよくなりますように。
今月は女性向けのコミュニケーションのセミナーが
続きましたが、
男性にも身につけていただきたいなぁと思います。