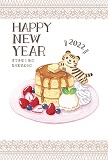ともに満ちる年に
2022年も静かなお正月を迎えています。
窓から青空と白い雲を見上げて、
どんな年にしたいかなぁと思いを巡らせると
「ともに満ちる」ということばが浮かびました。
世の中の流れは速いのでしょうが、
自分の心に正直に、趣くままに、
大事と感じることに丁寧にエネルギーを注いで、
小さな点が波紋のように少しずつゆっくりと
周りに広がっていくようなイメージで、
自分の心も相手の心も、ともに満ちるよう、
心をこめて関わりたいと思います。
昨秋ごろから、
私が長年経験を積んできたコーチングや研修が
思いのほか、今の時代の経営層や管理職の方々に
想像していた以上にお役に立つことを
改めて実感する機会が増えました。
私は自分から前に出るタイプではありませんが、
お役に立てるのであれば、何らかの形にして、
ご縁のある方々に提供していきたいと思います。
そのためにも、さらに学び続け、磨き続けて、
質を高めていきたいです。
自然に集まりにくいご時世だからこそ、
自分から「ひとのわ」をつなぐ機会を意識して
つくっていきたいと思います。
本年も、ひとのわと福住昌子とおつきあいいただけ
ますよう、どうぞよろしくお願いいたします。